1.コンタクトレンズの普及にともなって
コンタクトレンズの歴史は古くからあるものの、実用化され日常生活で普遍的な存在になったのはわずか50年余りです。
その後、ソフトコンタクトレンズも販売され、使い捨てコンタクトレンズが主流になり、乱視用や遠近両用レンズと種類も増え、使う側の選択肢が広がってきました。
更に、良質のコンタクトレンズが安価で購入でき、目に負担の少ないコンタクトレンズが開発され、コンタクトレンズのQOLは格段に便利になってきました。しかし、安易におしゃれ感覚でコンタクトレンズを使い、不適切な方法で行うと眼にダメージを与える可能性があります。

2.コンタクトレンズ装用の現状
- 現在、コンタクトレンズ装用者は全国で2,000万人超え、全世界で1億人以上います。
- レンズの種類とその割合は、数十年前はハードレンズ、従来のソフトレンズ、使い捨てソフトレンズがそれぞれ1/3でした。最近では従来のソフトコンタクトレンズは非常に少なくなり、ほぼ使い捨てソフトコンタクトレンズになりました。
- コンタクトレンズ装用者の低年齢化してきました。
- 「使い捨てレンズは清潔で安全である」と信じ無茶な使い方をする人がいます。レンズを装用する時に封を切って装用するので、従来の長く使うレンズより清潔である事は確かです。しかし、清潔であることと「長い時間の装用や、無理な使い方をしても安全である」ということは同じではありません。
- 購入方法の問題点が急増しています。コンタクトレンズは眼に直接触れる医療機器であり、心臓に埋め込むペースメーカーと同じグレードの高度医療機器です。正しく使用すれば視力矯正や外見の変化を楽しむことができますが、眼に負担をかける可能性もあることを忘れずに注意しましょう。便利なネットで購入する方が増えていますが、定期的に眼科検診をして購入することをおすすめします。
3.コンタクトレンズの歴史
| 1508年 | 画家であり科学者としても有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが大きなガラスの器に水を入れて、その中に顔をつけ、角膜を押しつけて物を見る実験を行っている。コンタクトレンズを作るための実験ではなかったが、これがコンタクトレンズの起源といわれている。 |
| 1636年 | デカルトが同じ様な実験を行い、コンタクトレンズの理論の基礎を築く。水中では角膜の屈折が無くなること、屈折異常が矯正されること、凸レンズによって拡像されることを発見している。 |
| 1801年 | トマス・ヤングが水量によって屈折度を変える事を発見 |
| 1827年 | イギリスのロイヤル天文学者ハーシェルが角膜保護の為の眼盃を作成 |
| 1888年 | スイス人眼科医のフィックがガラス製レンズを自分の眼につける実験をしたが2時間くらいしか装用できなかった。この時に使った「Einekontact-brille=接触した眼鏡」がコンタクトレンズの語源となる。 |
| 1926年 | 日本人では石原忍先生(色覚検査表を作った東大教授)がドイツ留学中にツアイスに自分の角膜にあったレンズを作って貰い自分の眼で実験して初めて報告した。 |
| 1929年 | ドイツのハイネ教授がカールツアイスに命じて角膜曲率半径(角膜の丸み)に合わせたガラスレンズのカーブを設定した。 |
| 1930年代 | プラスチック製コンタクトレンズが開発される:ハードコンタクトレンズ 第2次世界大戦で開発が一旦中止、戦後アメリカでアクリル性の角膜レンズ作成 (直径11mm、厚み0.4mmと大きなレンズであった。現在販売されている直径8.5~8.8mmになるのにさらに20年かかる。) |
| 1957年 | 日本で初めてレンズ生産 |
| 1960年代 | チェコでソフトコンタクトレンズ開発 |
| 1971年 | アメリカでソフトコンタクトレンズ発売開始 |
| 1973年 | 日本でも販売許可 |
| 1970年代後半 | 種々の酸素透過性ハードコンタクトレンズが開発、販売開始。 |
| 1990年代 | 使い捨てコンタクトレンズの発売・普及 |
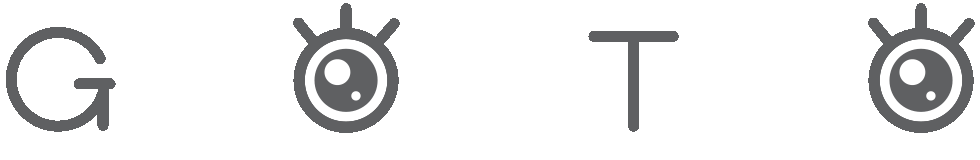

 03-5342-5801
03-5342-5801