1. 黄斑って何?
眼底網膜の中心にあるわずか2ミリ弱の少し凹んでいる場所で、網膜中心窩と呼ばれ、「視力」にとって1番大切な場所です。その窪みがあることで、網膜色素上皮層により綺麗な画像を投影でき、網膜の他の場所より良い視力が得られる構造になっています。
黄斑に体液(水分)や出血がたまったり、孔が開いたり、萎縮することで即、視力へ影響がでます。
2. 症状
黄斑に病気が出ると、視力低下、変視(歪み)、中心の色の異常、小視症がでます。両眼同時に生じる事は少ないので、両眼で見ている時には全く気がつかずに、たまたま片眼を隠した時に気づくことがあります。
3. 診断
OCT網膜断層撮影が1番役に立ちます。アムスラーチャートは診察室でも使いますが、患者さんが家で定期的にチェックできます。
4. 病気
(1)加齢黄斑変性
病態:加齢で網膜の老廃物(カス)が黄斑部に溜まり、見え方に悪さときたした状態です。
疫学:欧米では成人の失明原因の第1位です。日本でも高齢化と生活の欧米化に伴い患者数が増えてきて、日本でも第4位になりました。50歳以上の約1%に発症し、年齢と共に増加します。新しい治療法が開発され、以前と比べて、視力の維持が可能になって来ましたが、一旦、黄斑に病変が発症すると、完全に元には戻せないのが現状です。
病型:滲出型 黄斑部に新生血管からの血液や滲出物が溜まったもの
萎縮型
治療:抗VEGA療法
抗酸化サプリメント(ルテイン)の継続摂取
予防効果のエビデンスが示されている
大量摂取は肝機能低下などの全身に影響する報告もある
(2)黄斑円孔
黄斑部に小さな孔(直径0.1~0.5mm)ができ、文字が読みづらくなる病気です。周囲視野欠損なしの状態です。
・中高年に多い(中高年者の0.09%~0.3%)
・女性:男性 = 2~3:1
・強度近視に発症率が高い
・片眼
・診断:光干渉断層計(OCT)で診断
・治療:硝子体手術
(3)網膜前膜(黄斑上膜)
・黄斑部
・中高年に多い(40歳以上の20人に1人)白内障や老視が発症する頃と一致
・50~70歳の女性に多い
・症状:物が変形して見える。ゆっくり進行する。失明に至ることは少ない
・診断:光干渉断層計(OCT)で診断
・治療:黄斑前膜+内境界膜除去
(4)中心性漿液性網脈絡膜症
・脈絡膜血管からの滲出液が溜まり、小視症、視力低下などを自覚する
・比較的近視が軽度、男性、片眼、喫煙者、ストレスとの関与があると言われる。
・自然消退があるが、繰り返す場合もある
・早く消退するために 内服薬を処方する場合もある
・網膜造影検査で漏出点をレーザー治療する場合もある
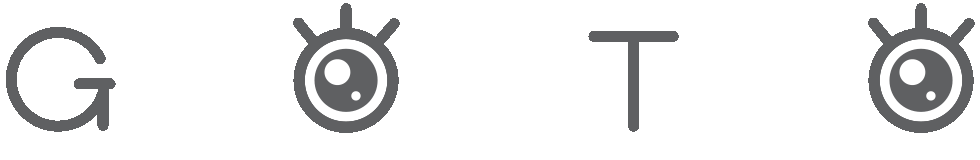

 03-5342-5801
03-5342-5801